本記事はこんな人におすすめ!
免許って、どのくらいの期間でとれるんだ?
結構忙しいけど、免許取れるのかな?
大学生になると、「そろそろ免許を取ろうかな?」と思う人が多いです。

私も大学生活中に運転免許を取得しましたが、授業やバイトとの両立に苦労しつつも、良い経験ができました。
この記事では、大学生の免許取得期間の平均、効率的に進めるコツ、そして通学と合宿プランの違いを詳しく解説していきます!
1. 大学生が運転免許を合格するのにかかる取得期間の平均
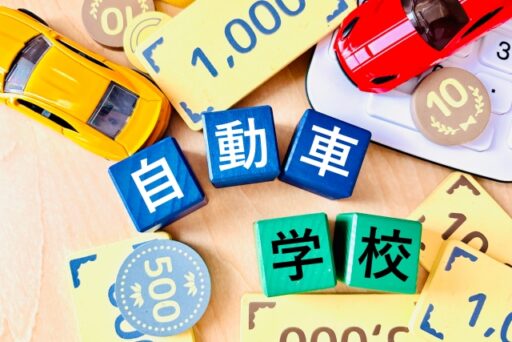
大学生が免許を取る場合、通学コースか合宿コースのどちらかを選ぶのが一般的です。
コースやスケジュールによって取得期間は変わりますが、おおよその目安は次の通りです。
1.1 通学コースの取得期間
多くの大学生が利用する通学コースでは、平日や週末に教習を進められます。
例えば週2〜3回のペースで通えば、1か月から3か月で取得可能です。

私もこの通学コースで通いましたが、冬の期間は高校生が多く、予約がなかなか取れない日も…。
さらに雪の影響で路上教習が大変だったこともあり、数か月かかりました。
特に路面が雪で覆われた時期は、交差点の右折や車線変更がとても怖かったです。
1.2 合宿コースの取得期間
短期間で免許取得を目指すなら合宿免許がぴったり!
2週間程度で卒業できるため、春休みや夏休みを利用して集中的に取得したい人に向いています。

友人が夏休み中に合宿で取得したときは「旅行気分で楽しめた!」と聞いて少しうらやましく思いました。
しかし、まとまった時間が必要なので、普段忙しい人にはややハードルが高いかもしれません。
2. 免許取得のプロセスとそれぞれのコツ

運転免許取得の流れは、主に以下の5ステップです。
1. 自動車学校への入学
2. 学科教習(座学)、技能教習(実技)
3. 仮免許試験
4. 学科教習(座学)、路上教習(実技)
5. 卒業検定と本免許試験
進行のコツやスケジュールの調整をうまく行えば、通学コースでも1か月半から3か月で取得が可能です。
ステップ1:自動車学校への入学
多くの大学生は大学の生協を通じて申し込むことで、割引を受けられます。

私も大学生協経由で申し込んだので、費用を少し抑えることができました。
ステップ2:学科教習(座学)、技能教習(実技)
学科教習は交通ルールや標識、安全運転の知識を学びます。
教習内容は基本的なものですが、交通事故のリスクや責任について考えさせられる内容も多く、興味深く学べました。
技能教習では、教官と一緒に運転技術を学びます。
初めて運転したときは、特にハンドル操作やブレーキのタイミングが難しく、苦労しました。
特に「S字カーブ」と「縦列駐車」は多くの人が苦戦するポイントです。

私はハンドルを切るタイミングを何度も練習し、教官の指示に従って少しずつコツを掴んでいきました。
私の場合は初日から運転し始めたのですが、いきなりすぎてとても怖かったですね…。
初日、助手席で教官が運転しているのを見て、「こんな感じなんだ~」と思っていたら。
「じゃあ運転してみましょうか?」と言われて、いきなり?!とびっくりしました(笑)。
ステップ3:仮免許試験
仮免許試験は、教習の中でも緊張する場面の一つ。
筆記試験と実技試験があり、無事に合格すると路上教習がスタートします。

私は筆記試験に苦手意識があったので、問題集をしっかり勉強しました。
ステップ4:路上教習、学科教習
路上教習は、実際の道路で運転するため最も緊張しました。
路上教習は緊張しますが、教官の指示に従いながら確実に運転技術を身につけていくことが大切です。
仮免教習の前も同様ですが、路上と学科教習は同時進行します。

私が通った冬の期間は、雪で道が滑りやすく、特に右折や左折のときに注意が必要でした。
ステップ5:卒業検定と本免許試験
最終的に卒業検定と本免許試験に合格すれば、念願の運転免許が取得できます。
卒業検定はこれまでの学びを総まとめして臨むため、しっかりと復習して試験に備えましょう!
3. 通学コースと合宿コースのメリット・デメリット
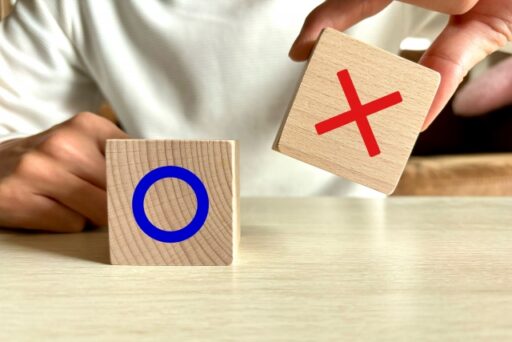
通学コースと合宿コースにはそれぞれ良い点があるので、しっかり悩んで、自分に合ったコースを選択しましょう!
3.1 通学コースのメリットとデメリット
3.2 合宿コースのメリットとデメリット
3.1 通学コースのメリットとデメリット
・授業やバイトと両立しやすい
・自分のペースで進められる
・取得期間が長め
・混雑時期は予約が取りにくい

私の場合は、冬場は予約が取れないことも多く、教習が進まない時期がありました。
3.2 合宿コースのメリットとデメリット
・2週間ほどの短期間で取得できる
・集中的に取り組めるため早く終わる
・まとまった時間が必要
・長時間の教習に集中する必要がある
4. 効率的な免許取得のポイント
効率よく運転免許を取得するためにも、意識したほうが良いことはたくさんあります。
運転免許を申し込む前に、意識してほしい点は以下の3つです!
4.1 長期休みの有効活用
4.2 通いやすい教習所を選ぶ
4.3 学習と教習のバランス

それぞれよく考慮して、自身に合った教習所で、免許取得頑張りましょう!
4.1 長期休みの有効活用
春休みや夏休みなどの長期休みを活用すると、一気に教習を進められます。
大学の学業と両立する場合でも、長期休みを有効に使うとスムーズに進められるでしょう。
4.2 通いやすい教習所を選ぶ
通学のしやすさは大切なポイントです。

私の場合は、自転車や送迎バスを使って通っていましたが、近い場所であればさらに時間を有効に使えたかもしれません。
4.3 学習と教習のバランス
座学も含まれる免許取得では、学科教習と技能教習の両方でコツコツと進めることが必要です。
技能と学科教習のすべてが終了していないと、仮免や本試験は受けられないです。

友達に「技能ばかりが進んで、学科が全然進んでいないため、試験が受けられない…」。となっている人がいたので、バランスよくこなしていくのが、最も効率的です!
5. 大学生におすすめの自動車学校の選び方

自動車学校を申し込むうえで、様々悩むかと思います。

私自身、どの自動車学校に通うべきか悩みましたが、入校した後にこうすればよかったなと、後悔してしまったこともありました。
私の経験も含めて以下では、自動車学校のおすすめの選び方を解説します!
5.1 大学から近い立地を選ぶ
5.2 学割や割引制度があるか
5.3 予約の取りやすさ
5.1 大学から近い立地を選ぶ
通いやすい立地の学校を選ぶと、移動時間を短縮でき、大学の予定に合わせて通いやすくなります。

私の場合は、大学からはかなり遠い場所にありましたが、自動車学校のバスの送迎を利用していたので、大学の講義後でも通いやすかったです。
5.2 学割や割引制度があるか
大学生向けの割引や特典がある学校も多いです。

私は大学生協経由で申し込んだことで、割引が適用され少し安く済ませました。
5.3 予約の取りやすさ
混雑しやすい時期でも予約が取りやすい教習所はスムーズに進めやすいです。
特に通学コースでは予約状況が大きく影響するので、事前に確認しておくと良いでしょう。

私が入校した自動車学校では、人が多く、予約が取れない日が多々ありました…。
6. 免許取得後の活用法と注意点

免許を取ったら早速ドライブに行きたくなるものですが、新米ドライバーとしての注意点もあります。
初心者マーク:
取得後1年間は初心者マークをつけて運転することが義務付けられています。
高速道路での運転:
高速道路に初めて行く際には、速度の調整や車間距離に特に気をつけましょう。
自信を持ちつつも慎重に:
取得直後は運転に慣れていないため、無理のないスピードと適切な間隔を保つことが大切です。
最後に
大学生にとって運転免許の取得は手間もかかりますが、大学生活の合間に効率的に進めることで、多くの人がスムーズに取得しています。

私の実体験からも、計画的に進めれば取得までの道のりはしっかりとクリアできるはずです。
免許取得を検討している方は、自分に合ったスタイルで一歩踏み出してみてください!



コメント